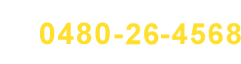不動産取得税がかからないケースを詳しく解説|久喜「正直」不動産ナビ
不動産取得税がかからないケースとは、どういったケースになるでしょうか。
不動産取得税を納付する必要が出てくるケースとして総務省は、「土地や家屋の購入もしくは贈与、家屋の建築などで不動産を取得した場合」としています。となると、新築住宅を購入したときや、中古住宅を購入したとき、あるいは家の相続が発生したときなどが思い浮かびます。
しかし、こうした不動産の取得にあたって、一定の条件を満たした場合は、不動産取得税がかからないケース、あるいは不動産取得税の税額を軽減できるケースが存在します。
この記事では、不動産取得税とはどのようもので、どう計算され、どのような条件を満たせば控除が受けられるのか、これから不動産を取得する予定のある方へ向けて詳しく解説します。
不動産取得税とは
不動産取得税とは、不動産、つまり土地や建物を取得する際に、その不動産が所在する都道府県といった自治体に納付する必要のある税金のことです。地方自治体に納付する税金は地方税と呼ばれ、不動産取得税の他にも住民税などがあります。
不動産取得税の基本情報
その名の通り不動産取得税とは、不動産を取得した際にかかる税金ですが、ではここでいうところの「取得」とは具体的にどういったものを指すのでしょうか。
不動産取得とは、新築住宅の購入、あるいは中古住宅の購入など、その方法にかかわらず、不動産を取得した場合のことを言います。この「取得時」にかかる税金なわけですから、支払う必要がある場面は取得時のみ、つまり一度きりとなります。
不動産取得税の支払いは、取得後の確定申告時に税額が決定され、取得からおおよそ1年以内に送付されてくる納税通知書によって行います。このため不動産取得税は、電気代などのように銀行口座から自動引き落としになるようなことはなく、県税事務所やコンビニに足を運び、自分で納付する必要があります。
ただ自治体によっては、クレジットカードや電子マネーを使った決済も可能なため、昔よりは手続きが手軽になっています。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、取得した不動産の評価額に基づいて決定されます。
ここでいう評価額とは、その不動産の価値がどれくらいなのかを客観的指標に基づいて決定した金額であり、主に税金を算定するために使用される数値です。評価額は「固定資産税評価額」とも呼ばれ、その不動産の市場価格とは別のものとなります。
端的に言えば、たとえ不動産の購入金額が安かったとしても、この固定資産税評価額が高額であれば、不動産取得税が高くなってしまう可能性もある、ということです。
こうしたことから、不動産を取得した際に、不動産取得税が高額になってしまい、思わぬ出費に困惑してしまう、といったケースもよく見られます。そうならないため、不動産取得税の計算方法を知っておくのが得策です。
不動産取得税の計算方法は基本的に、下記となります。
不動産取得税 = 不動産の評価額 ✕ 税率(4%)
ただし、令和9年3月31日までに取得した住宅用の土地や住宅は、上記のうち税率が3%で計算されます。つまり、下記の計算式です。
不動産取得税(令和9年3月31日まで取得) = 不動産の評価額 ✕ 税率(3%)
このため、例えば上記期間内に、評価額が1,200万円の不動産を取得した場合は、税率が3%となるため、
評価額1,200万円 ✕ 税率3% = 36万円となります。
参考:「不動産取得税に係る特例措置」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000020.html
不動産取得税の計算方法は基本的にこのようなものですが、金額が意外と高そうだと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし条件さえ整っていれば、不動産取得税がゼロまで控除される、つまり不動産取得税がかからないケースもあります。
不動産取得税がかからないケース
相続による不動産取得
地方税法第73条の2によれば、不動産取得税とは「土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したとき」、その取得者にかかる税金とされており、取得方法における有償・無償の別(=売買か贈与か)、あるいは登記の有無は問わない、とされています。
この条件に当てはまらない不動産取得のケースの一つが、相続で不動産を取得した場合です。相続は、売買ではなく、また贈与でもないため、不動産所得税の支払いは不要となり、納税通知書が送られてくることはありません。
ただし、相続した不動産の評価額が大きい場合などは、不動産取得税は不要でも、相続税の納税が必要になるケースがあるため、注意して下さい。
また、原則60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に、「相続税精算課税」制度を選択して不動産を贈与した場合、こちらは「贈与」の定義に当てはまることになるため、納税は必要になることに注意が必要です。
参考:「No.4103 相続時精算課税の選択」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
特定の新築住宅に対する軽減措置
相続の場合以外にも、不動産取得税を減税させるために設けられた特例としての優遇措置、つまり不動産取得税の軽減措置制度が当てはまるケースがあります。
こうした場合は、不動産取得税計算において、固定資産税評価額から控除額が差し引かれることになります。もちろん、税金の控除額が評価額を上回れば、納税額をゼロにすることも可能となります。
まず新築住宅の購入時については、原則として1200万円を建物の評価額から控除することが可能です。この特例は「住宅用地特例」と呼ばれます。主な適用条件としては下記となります。
- 個人の居住を目的とした住宅である
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
この場合は上記の通り1200万円が評価額から控除されます。つまり、評価額が1200万円以内であれば、控除額が評価額を上回るため、建物にかかる不動産取得税はゼロになります。
なお購入する家屋が「長期優良認定住宅」に合致する場合、控除額は1300万円まで拡大されます。つまり、優良な家屋を建てることにより、控除が100万円増額されるということです。
不動産取得税は建物と土地を別々に計算するもので、ここまでの内容は建物にかかる軽減措置となりますが、これとは別に、土地の軽減措置を受けられる条件というものも存在します。こちらの条件は下記です。
- そこに建てられた住宅が建物の軽減措置の条件を満たしている
- 土地購入から建物の新築までが3年以内
- あるいは建物の新築から土地購入までが1年以内
こちらによる控除額の算出は、下記のいずれかのうち金額が大きい方となります。
- 45,000円
- (土地1㎡あたりの固定資産税評価額 ✕ 1/2) ✕ (住宅の課税床面積 ✕ 2(積の上限は200㎡)) ✕ 3%
このいずれかによって出した控除額を用い、下記のように土地の不動産取得税を算出します。
土地の不動産取得税 = (土地の固定資産税評価額の半分) ✕ 3% ― 控除額
このようにして、新築物件の不動産取得税は各種軽減措置によって控除が可能です。同じ新築でも条件によって控除額は変わってくることに注意しましょう。
中古物件に対する軽減措置
対して中古物件の建物では、下記のような条件を満たすことにより、不動産取得税の軽減措置を受けられます。
- 個人の居住を目的とした住宅である
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 新耐震基準への適合もしくは既存住宅売買瑕疵保険への加入
最初の二つの条件は新築物件と同じですが、3つ目の条件は中古物件に独特のものとなります。
ここでいう「新耐震基準」とは、昭和57年1月1日以降に建築された物件に適用されるようになった、新たな耐震基準のことです。
つまり、それ以降に建築された物件であれば、基本的に条件を満たしていると判断することができます。
あるいは昭和56年12月31日以前に建てられた建築であっても、上記の新耐震基準に適合しているか、既存住宅売買瑕疵保険への加入が証明されれば、軽減措置の対象となります。
万が一その物件が新耐震基準に適合していなくても、入居前に新耐震基準を満たす補修を行えば、条件を満たすことになります。
なお、こちらにおける建物の不動産取得税控除額は、下記のように、新築した日に応じて変動します。
- 1997年4月1日以降の新築物件は、控除額1200万円
- 1989年4月1日から1997年3月31日の新築物件は、控除額1000万円
- 1985年4月1日から1989年3月31日の新築物件は、控除額450万円
- 1981年4月1日から1985年3月31日の新築物件は、控除額420万円
- 1976年4月1日から1981年3月31日の新築物件は、控除額350万円
これらは建物の軽減措置であることに注意して下さい。土地のほうの控除の仕組みは、新築と同様となります。
家屋や土地の価格が免税点未満の場合
所得した不動産の価格が、「免税点」と呼ばれる水準に満たない(未満である)場合も、不動産取得税は免除されます。
こちらは、土地であれば価格が10万円未満、家屋であれば23万円未満が、免税点未満となります。なお家屋のみの購入の場合は、12万円未満が非課税です。
事業用不動産の取得
事業用に取得した不動産についても、不動産取得税がかからないケースが存在します。
ただし、こちらは対象が特定の法人の場合に限り、どんな事業内容であっても対象になる、という措置ではないことに注意してください。
対象になる法人とは、下記のようなものです。
- 保育、教育などに不動産を利用する学校法人
- 境内地として不動産を利用する宗教法人
- 老人ホームや児童養護施設として不動産を利用する社会福祉法人
これらに当てはまる場合なら、事業用に取得した不動産の不動産取得税は非課税となります。
またこうした場合においては、その法人の本来の事業が、条件となっている用途と合致していることも条件となります。
上記のような学校、宗教、社会福祉といった法人であっても、本来の事業とその不動産の用途が異なるものである場合は非課税とはならず、課税対象になることに注意しましょう。
不動産取得税の軽減措置申請
軽減措置の申請方法と必要書類
不動産取得税の軽減措置については、不動産取得から原則60日以内に、管轄となる都道府県税事務所に必要書類を提出する必要があります。
この際に必要な書類などは、主に以下のようなものとなります。
- 不動産取得税減額申告書(土地と建物それぞれ一通)
- 納税通知書
- 印鑑
- 土地と住宅の売買契約書
- 住宅の登記事項証明書
- 取得した不動産住所に移転済みの住民票
- 耐震基準適合証明書(中古戸建の場合)
- 長期優良認定住宅認定通知書など(長期優良認定住宅の場合)
自治体によっては、必要な書類の内訳が異なる場合があります。
実際に書類を提出する際は、それぞれの不動産が所在する自治体の県税事務所などで確認するようにしましょう。
軽減措置適用の具体的な計算例
軽減措置を適用した際に、不動産取得税がいくらになるのかは、次のような計算式で求めることができます。
まず、控除を受ける前の不動産取得税を計算します。その計算式は次となります。
- 固定資産税評価額 ✕ 3% = 不動産取得税(軽減措置適用前)
これを踏まえ、下記のような物件で軽減措置適用を行った場合を考えてみます。
|
購入日 |
2025年4月1日(建売新築) |
|
面積 |
床面積 120㎡ 土地面積 160㎡ |
|
固定資産評価額 |
建物 1,500万円 土地 1,200万円 |
このとき、不動産取得税は下記のようになります。ここでは新築住宅軽減による建物への1,200万円控除、また土地に対する控除を織り込んで計算しています。
- 建物の不動産取得税
(万円 ― 控除万円)
- 土地の不動産取得税
- 1,200万円 ✕ 1/2)✕ 3% ― 控除22万5,000円 =(―4万5,000円なので) 0円
※土地の軽減額は下記のように計算しています。
- (1,200万円÷160㎡✕1/2)✕ (160㎡✕2 ※上限200㎡)✕ 3% =22万5,000円
- これは4万5,000円より大きいため、軽減額は22万5,000円
不動産取得税に関するよくある質問
ここまでの説明内容を踏まえたうえで、不動産取得税について考える際によく出てくる疑問をまとめました。
不動産取得税がかからない条件とは?
不動産を相続した場合、不動産取得税を納税する必要はありません。
不動産取得税の納税義務が発生するのは、土地や家屋といった不動産の取得、すなわち購入・贈与・家屋新築による取得といった場合に限り、こうした定義に相続は含まれません。
ただし、不動産を相続した場合、その不動産の評価額によっては、不動産取得税とは別に「相続税」という税金の納税義務が発生することがあるため注意しましょう。
相続したケースでなくても、軽減措置制度の利用により控除が発生し、その控除額が原則的な不動産取得税の金額よりも大きくなれば、こちらも納税は必要なくなります。
この場合は、新築住宅の場合のほうが、中古住宅よりも控除額が大きくなるのが一般的です。
中古住宅を購入する場合でも軽減措置は受けられますが、この場合、築年数(いつ建てられたか)、および耐震基準への適合度合いによって、控除額は上下することを覚えておきましょう。
家屋や土地の価格が免税点未満である場合や、購入者が特定の法人に該当し、不動産物件を特定の目的に活用する場合なども、不動産取得税の免除対象になります。ただしこれらは特殊なケースといえ、多くの住宅用不動産購入者にとってはあまり考えることのないものと言えるかもしれません。
不動産取得税の通知が届かない場合
通知が来ないということは、その不動産取得に関して通知すべき税金がない、という意味合いとなり、軽減措置などによって納税の必要な金額がゼロ=免税になっている、という状況が考えられます。
この場合はもちろん、納税の義務はありません。
納税通知書は、不動産の取得から1年以内に届く場合が多いと考えられます。
1年が経過しても納税通知書が届かない場合は、不動産取得税の納付義務がなかったものと考えてよいでしょう。
ただし、通知が届かないと考えていたが、通知書を紛失していた、通知書が届いていることを忘れ放置していた、といった場合も少なくありません。
通知書が届いた際には、見えるところで保管したり、すぐに支払いをおこなったりと、忘れないよう注意しましょう。
税金は納付義務があり、それを怠った場合は納税滞納という扱いになり、追徴課税を受ける危険性があります。
こうしたトラブルを防ぐため、納税通知書が届かない場合は、不動産の管轄である県税事務所に連絡をし、不動産取得税など納税が必要な金額がないか確認してもらうのがよいでしょう。
軽減措置の期限について
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、不動産取得から60日以内に申告をする必要があります。つまり、軽減措置を受けるための期限は60日、ということです。
軽減措置の申告に必要な書類は不動産取得税と兼用であるため、これらはいっしょに申告を行うことになります。注文住宅などであれば、建物が未登記のために取得税申告の猶予が発生する場合もありますが、その場合は別途、提出の必要な書類があるため、こちらも県税事務所などに相談するのがよいでしょう。
申告書類の記入方法、手続きのやりかたについては、個人であれば戸惑うことも全く珍しくありません。そうした場合は、ハウスメーカーや不動産会社、司法書士といった専門家に相談し、期限を過ぎることなく提出するようにします。
なお、これらの申告手続きが正当な事由なく遅延した場合は、過料(金銭的な罰則)が課せられることもあるため、注意して下さい。
まとめ
住宅の取得を考えている方にとって、不動産取得税がかからないケースを把握しておくことは、非常に大切です。
とくに、取得する住宅をこれから絞り込む際や、初期費用をしっかり用立てておきたい場合などは、不動産取得税がかからない選択が可能になることで、経済的負担を減らすこともできるはずです。
地域によっては、特例や減免措置が設けられていることもあります。
そのため住宅の購入検討時は、不動産会社や公的機関に相談することで、その地域の制度を確認しておくのもよいでしょう。
こうした不動産取得税のかからない住宅取得や、その他不動産関連の様々な手続きにおいて、久喜市で多大な実績を有しているのが、フジハウジングです。適切な専門家の相談などを含め、不動産取得税やその他のことについて専門家に相談したいとお考えの方は、フジハウジングへご相談下さい。 https://fujihousing.net/