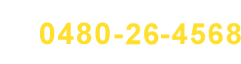不動産利回りの計算方法と相場を徹底解説|久喜「正直」不動産ナビ
不動産利回りとは、ある物件を資産として保有した場合に、その物件の購入価格に対し、1年間でどれくらいの金額が戻ってくるかの割合をいいます。
この不動産利回りは、不動産投資において最も重要なポイントです。
しかし、とくに不動産投資を始めたばかりの方は、様々な物件の不動産利回りをどのように評価すればよいのか、正しく理解していないケースが意外に多く見られます。
本記事では、不動産投資の成否を左右する「利回り」について、不動産投資を始めたばかり、あるいは始める前の方から、すでに不動産投資を行っている方までを対象に、わかりやすく、かつ詳しく解説していこうと思います。
不動産利回りとは何か
不動産利回りとは先述の通り、その物件の購入価格に対し、1年でどれだけの金額を収入として回収できるかの割合を示します。
不動産利回りは、1年あたりの収益(年間収益)を不動産価格で割った結果の数字を%(パーセント)で表します。例えば不動産利回りが10%なら、購入価格に対し1年あたり10%が回収でき、10年で100%、つまり全額が回収できる、という計算になります。
例えば、購入価格が4000万円の物件があり、この不動産利回りが12.5%であったとします。この物件の年間収益を計算する最も基本的な式は、次のようなものです。
不動産利回りと年間収益:
不動産価格4000万円 ✕ 不動産利回り12.5% = 概算年間収益500万円
このように、この不動産を一年間保有した場合の概算収益は500万円となります。
不動産投資に限らず、投資行動においては、この「利回り」をどのように捉えるかが重要なポイントとなってきます。
さらに詳しく説明するならば、不動産投資においては次の三つの「利回り」が存在します。
- 表面利回り
- 実質利回り
- 想定利回り
次項で、それぞれ詳しく解説していきます。
表面利回りとは
表面利回りとは、不動産投資における収益を計算するための、最もシンプルかつ簡単な指標です。
表面利回りは、次のように、年間家賃収入と物件価格という二つのファクターを用いれば、比較的簡単に計算できます。
表面利回り(%)=(年間家賃収入÷物件購入価格)✕100
この式に具体的な数字、例えば、前項で示したのと同じ物件
・年間家賃収入500万円
・物件購入価格が4000万円
を入れると、次のようになります。
表面利回り(%)=(年間家賃収入500万円÷物件購入価格4000万円)✕100
↓
表面利回り(%)=12.5%
なお、前項で例示した「最も基本的な計算式」で求めた利回りは、表面利回りにあたります。
表面利回りの特徴は、「シンプルで簡単な指標」であることと、「実際の収益とは異なる数字になる可能性があること」の2点です。
表面利回りは、実際に物件を運用した際に、購入費用とは別にかかってくる修繕などの経費、あるいは空室リスクといったものを考慮していないのです。
実際の利回りと異なるものであるのに、なぜ表面利回りという概念が存在するのでしょうか? それは、とにかく「わかりやすく」、物件同士を比較する際などに「簡単に評価ができる」ためです。
例えば、投資物件を物色する初期段階など、たくさんの物件から運用に適した物件を絞り込む際などには、この表面利回りが大いに役立ちます。
実質利回りとは
これに対して、実際に得られる収益から、必要経費を差し引いたものを、実質利回りと呼びます。
例えば、表面利回りを用いて絞り込んだ複数物件を、実際に購入・保有する一つの物件に絞り込む場合などは、実質利回りを出して比較するのが懸命です。
あるいは購入後の運用時点でも、この実質利回りは様々な場面で確認が必要となってくるものです。
実質利回りの計算における「必要経費」には、次のようなものが入ってきます。
- 購入時の諸費用(登記、司法書士報酬、不動産仲介手数料など)
- 年間運営費
- 固定資産税
- 火災保険・地震保険料
- 修繕費・修繕積立金
このうち「購入時の諸費用」は物件購入時のみに発生します。
その他の費用に関しては、1年毎、あるいは数年ごとに、継続して発生する費用となり、実質利回り計算時には、それぞれの費用を1年あたりにならした数字を出し、それを「年間諸費用」として計算に入れるなどするのが一般的です。
実質利回りを計算するために、どの項目をどこまで入れるべきか、というのは、特に厳密な定義があるわけではありません。
とはいえ、こうした経費を詳細に入れ込んで実質利回りを計算することで、より現実的な利回りが見えてくることになります。
実質利回りの計算は、次のような式で行います。
実質利回り(%)=(年間収入―年間必要経費)÷(物件購入価格+購入時諸費用)✕100
ここでも、前項までの例と同じ、
・物件購入価格4000万円
・年間収入500万円
こちらの物件の数字を入れて、あらためて確認していきます。
ただし今回は実質利回りを確認したいので、「年間諸費用」および「購入時諸費用」という項目も組み入れます。
例えば、次のような物件があるとします。
- 年間収入:500万円
- 年間諸費用:50万円
- 物件購入価格:4000万円
- 購入時諸費用:400万円
この数字を、上記の実質利回り計算式に代入すると、次のようになります。
実質利回り(%)=(年間収入500万円 ― 年間必要経費50万円)÷(物件購入価格4000万円+購入時諸費用400万円)✕100
↓
実質利回り(%)=(450万円)÷(4400万円)✕100
↓
実質利回り(%)= 約10.2%
年間諸費用と購入時諸費用という二つの出費項目が入ったことにより、実質利回りは10.2%と、表面利回り(12.5%)より低くなりました。
このように、実質利回りを計算することにより、項目が増える分少しだけ手間がかかるものの、表面利回りよりもリアリティのある数字を確認することができます。
想定利回りとは
もう一つ、想定利回りというものについても説明します。
想定利回りとは、一棟マンションや一棟アパートといった集合住宅への投資に関し、部屋が満室(=空室のない、全ての部屋に入居者がいる状態)と想定したときに得られる利回りのことをいいます。こちらの計算式は次のようになります。
想定利回り(%)=満室想定の年間家賃収入÷物件購入価格×100
ここで注意したいのは、想定利回りではあくまで「満室の場合」を想定して計算が行われているという点です。
一棟マンションや一棟アパートといった集合住宅への投資においては、満室を目指した運営がなされるのは当然ですが、実際には常に満室の状態が続く状態は多くありません。
むしろ地方の物件などでは、慢性的に空室が発生する物件も数多く見られます。
このため想定利回りは、入居者を確保できるかどうかという点で、実際に物件を購入したあとの利回りよりも高くなってしまう(=実際に得られる利回りが想定利回りより低くなってしまう)点に注意すべきです。
また想定利回りは上記の通り、表面利回りと同じような計算で行われる場合が一般的で、物件購入時の費用や年間で出ていく諸費用は計算に入っていません。
この点でも、実際の運営後に入ってくる利回りは、想定利回りを下回ることがほとんどです。
不動産会社が物件広告に掲載する利回りは多くの場合、計算がシンプルでわかりやすい表面利回り、もしくはこの想定利回りが掲載されています。
そのため交渉に当たる際などは、広告に記載の利回りがどこまでの費用を織り込んでいるのか、また考えられる実際的な費用を織り込んだ実質利回りがいくらくらいになるのか、不動産会社に確認しておくのがよいでしょう。
不動産利回りの相場
次は、不動産利回りの相場について考えてみましょう。
物件ごとに異なる利回りですが、その水準には、様々な条件に応じた傾向(=相場)もあります。例えば、新築か中古物件か、あるいは、どんな地域・エリアに物件が所在しているか、といった条件で、利回りの相場は上下する傾向にあります。
ここでは、そうした利回りの相場に影響する諸条件について説明します。
新築物件の利回り相場
新築物件の利回りは一般的に、低くなります。
物件も設備も最新であり、かつ過去に瑕疵が起きた可能性もゼロに近い新築物件は、入居者も購入希望者(投資家)も集まりやすくなります。このため、物件を販売したい不動産会社は強気な価格、つまり、より高い購入価格を設定したくなります。
購入価格が大幅に高くなると、利回り(年間家賃収入÷購入価格)は他の中古物件よりも低くなります。これが、新築物件の利回りが低くなりがちな理由と言えます。
新築かどうかに加え、立地や設備といった条件によっても利回りは変動するため、新築物件の利回り相場をいちがいに述べるのは難しいですが、参考まで、新築アパートの実質利回りについて述べるなら、次のようになります。
|
新築アパートの利回り相場 |
3%〜5% |
|
理想的な利回り |
5%〜8% |
|
最低でも確保したい利回り |
3%程度 |
中古物件の利回り相場
一方で、中古物件の利回りは一般的に、新築よりも高くなります。
物件も設備も最新とは言えず、かつ過去に瑕疵が起きた可能性も存在する中古物件は、新築と同じ購入価格にしていると購入希望者(投資家)が集まりにくいため、物件を販売したい不動産会社は、より低い購入価格を設定することが多くなります。
購入価格が大幅に安くなると、利回りは高くなります。これが、中古物件の利回りが高くなりがちな理由です。
こうしたことを考えるならば、単に利回りが高いからといって安直に手を出すのは、注意が必要です。
例えば、賃貸を借りたい人が少ない地域であるために空室リスクが高い、過去に瑕疵が起きたため入居者がつかないなど、高利回り物件を見つけた際には忘れずに確認を行いましょう。
具体的には、高利回り物件を見つけた際は、下記の項目を確認しましょう。
- 設備が古くないか(風呂釜、浄化槽、受水槽、キッチンや水回りなど)
- 建物の状態が悪くはないか(室内修繕がされていない、外壁にヒビや剥がれ、シロアリ被害など)
- 事故物件ではないか(自殺や他殺といった事件による、告知を要する瑕疵がないか)
- 入居者属性に問題がないか(トラブルの起きがちな入居者がいないか)
いくら高利回りでも、こうした条件が当てはまるようであれば、新しく入居者を見つけるのに苦労したり、あるいは購入後の修繕や保全、対応に多額のお金がかかったりといったリスクに見舞われる可能性があります。
要は、高利回り物件とは、しばしば安売りしなければ売れない物件の可能性もある、ということです。
高利回り物件が必ずしも問題を抱えているというわけではありませんが、利回りの高めな物件を検討する際は、こうしたポイントについて不動産会社によくよく確認を求める必要があるでしょう。
中古物件についても、様々な条件で変動する利回りの相場をいちがいに述べるのは難しいですが、参考まで、中古アパートの実質利回りについて述べるなら、次のようになります。
|
中古アパートの利回り相場 |
5%〜8% |
|
理想的な利回り |
8%〜10% |
|
最低でも確保したい利回り |
5%程度 |
エリア別の利回り相場
新築・中古という尺度の他に、不動産利回りに大きな影響を及ぼすもう一つのものが、不動産のある地域です。
一般的には、人口密度が高い地域ほど、そこに住もうとしている人が多いと考えられ、そのぶん不動産価格は高くなります。不動産の購入価格が高くなれば利回りは下がることになるため、都市圏は利回りが低い、地方は利回りが高い、と言えます。
参考まで、一棟アパートの利回り平均を日本全国のエリア別に示した表を、次に掲載します。イメージをつけやすくするため、物件価格も併記します。
エリア別 一棟アパート利回り・価格 平均(2024年5月期)
|
地域 |
利回り(%) |
価格(万円)) |
|
全国 |
8.07 |
7,861 |
|
北海道 |
10.98 |
4,509 |
|
東北 |
11.34 |
4,964 |
|
首都圏 |
7.54 |
8.373 |
|
信州・北陸 |
15.14 |
4,439 |
|
東海 |
8.80 |
6,506 |
|
関西 |
8.46 |
7,623 |
|
中国・四国 |
13.06 |
4,169 |
|
九州・沖縄 |
9.47 |
6,400 |
この表を見るとわかるのは、人口過密な首都圏の利回りが低く(7.54%)、人口密度の低い信州・北陸の利回りが高い(15.14%)という傾向です。
首都圏のように人口が過密だと、住みたがる人が多くて空室率が低下、そのためアパートの設備投資(リフォームなど)や新築なども増えて価格が増加、さらに利回りが低下する、といったスパイラルが発生している可能性もあるでしょう。
一方で信州・北陸や中国・四国といった地域では、人口過密でなく不動産ニーズも緩やかであるために、アパートの設備投資(リフォームなど)や新築などが行われる頻度も減り、その結果として価格が低下し、さらに利回りが上昇する、という可能性も考えられます。
【参考】収益物件市場動向マンスリーレポート2024年5月期(不動産投資と収益物件の情報サイト 健美家 (けんびや)) https://www.kenbiya.com/doc/press/pre2024-06-03.pdf
理想的な不動産利回りを達成するためのポイント
このように、新築・中古、あるいは立地エリアといった様々な条件で変動する不動産利回りですが、理想的な不動産利回りの物件を見つけるためにはどのようなポイントに気をつければよいのでしょうか。
物件選びのポイント
投資・購入する不動産を選ぶ際には、不動産利回りだけを選定の基準としないことが、最も大切です。
収入にそのまま結びつくのは不動産利回りではありますが、いざ投資を始めても入居者がなかなか集まらないとか、修繕に多額の費用が必要になってしまったとか、そのような事態におちいってしまうと、いくら利回りが高かろうが思うような収入が得られません。
そのため、不動産物件を選ぶ際は、下記のようなポイントをよく吟味しましょう。
- 築年数
- 立地条件
- 耐震基準
- 周辺環境
- 瑕疵の有無
他の投資行動とは異なり不動産投資は、保有した資産(=不動産物件)を放って置くだけというわけにはいきません。入居率を高め、空室リスクを抑制することで、はじめて安定した収入に繋がってきます。そのために、こうしたポイントはよく確認しておくのが懸命です。
管理コストの削減方法
不動産利回りをできるだけ高く保つためには、管理会社の選定に注意を払うのが重要と言えます。
管理会社の手数料によって、管理コストは増減します。手数料が安ければ目先の管理コストも減少はしますが、一方で不動産保有者の手間が増えるなどのデメリットも考えられます。
あるいは自主管理(管理会社を介さない)であれば手数料もゼロにはなりますが、この場合は大きな手間や労力が必要になります。手数料とサービス内容のバランスを見たうえで、自身のライフスタイルに最も合った管理会社を探すのが良いでしょう。
また管理コストについても、前掲の様々なポイント(築年数、立地条件、耐震基準、周辺環境、瑕疵の有無)を押さえておくことが重要になってきます。というのも、これらのポイントを押さえれば、入居者が集まりやすいのはもちろんのこと、退去者が出るリスクも減らせるし、設備老朽化や災害といったタイミングで必要な追加コストも抑制できるからです。
物件購入費用のような高額なコストと比べると、毎年かかってくる管理コストは桁が一つか二つほど低額になってくるので、さほど気にしないという投資家も散見はされます。しかし、利回りが仮に10%だったとしても、購入費用を全額回収する(得られた利回りが累積で100%に達する)には表面利回りで10年かかる計算となります。
長期保有を前提とすることの多い不動産投資においては、購入価格のほか管理コストについても、抑制のためしっかりと対策を行うのがよいでしょう。
まとめ
不動産投資における利回りは、その投資活動を成功させ、自身の生活を安定させる重要なポイントといえます。
そのため不動産投資については、利回りの計算方法や、利回りの相場感覚、あるいは利回りに影響を及ぼす新築・中古や立地エリアといった条件について知っておくことが、必要になります。
そうすれば物件の収益性が理解でき、どのような物件を選べばよいか、どのような運営を行えばよいか、というイメージができるようになるためです。
不動産投資を行う際には、利回りや価格だけでなく、リスクを念頭に置くことも大切です。
本記事で解説したポイントを意識して、知識や経験に富む不動産会社と関係を持つことが出来れば、良い物件選びや安定した収益獲得が必ず実現するはずです。
とくに、久喜市の不動産事業においてフジハウジングは多大な実績を有しており、たくさんのお客様の不動産投資を成功させています。不動産投資としての物件購入をお考えの方は、まずフジハウジングへご相談下さい。
久喜市の不動産取引についてはこちら https://fujihousing.net/